江華郷校(강화향교)
2024-09-20
仁川広域市 江華郡 江華邑 郷校キル 58
1127年(仁宗5)3月に賢儒の位牌を安置、位牌を祀り地方の人の教育のために高麗山の南方に郷校が建てられました。1232年(高宗19)に現在の甲串里に移されましたが、蒙古軍の侵攻により再び西島面に移されました。その後、江華郡へと移され、1624年(仁祖2)に江華留守(地方官)の沈悅が松岳山(現在の北山)の横に復元しました。1629年には江華府尹の李安訥(イ・アンヌル)が明倫堂を設立し、1688年(粛宗14)に留守の閔蓍重(ミン・シジュン)が 南門の近くに移しました。1731年(栄祖7)には、留守の兪拓基(ユ・チョッキ)が現在の位置に移し、1766年に留守の李溵(イ・ウン)が修復すると同時に小東門の外にあった碑石を現在の位置へ移しました。京畿道の文化財資料に指定されており、大正殿、明倫堂の東廡、西廡、祭器庫、厨房などが現存しています。前面5間、側面3間の切妻屋根から成る大正殿には五聖、十八賢の位牌が安置されています。朝鮮時代には国家から田畑や労賃・典籍などの支給を受け、教官が教育を行いましたが、現在は教育は行われておらず、春や秋に釈奠、1日・15日に焼香を行い、1名の典校と数名の掌議が運営を行っています。
舒川 馬梁里ツバキの森(서천 마량리 동백나무 숲)
2024-09-20
チュンチョンナム道ソチョン郡ソ面ソインロ235ボンギル103
* 鬱蒼と生い茂るツバキの森に出会える場所 *
舒川(ソチョン)八景のひとつに数えられる馬梁里(マリャンニ)ツバキの森は、天然記念物に指定されている場所です。
この森には樹齢およそ500年のツバキの木85本が8,265平方メートルの敷地に鬱蒼と生い茂り森をなしています。
3月下旬から5月初旬まで青々とした椿の葉の合間につつましやかに咲く紅色のツバキの花を楽しむことができます。小高い丘の上にある冬柏亭(トンベクジョン)に上ると西海(ソヘ)の青い海原や美しい夕日を眺めることができます。
特に目の前に浮かぶ島・オリョク島の風景と相まって、海原の風景も一枚の絵を見るような絶景を誇ります。
馬梁里ツバキの森の西側は風が強くツバキの木は数本しかなく、反対の東側にはおよそ70本のツバキの木があります。
チャノキ(茶の木)同様、ツバキ科ツバキ属に属するツバキは高さが7メートルほどまで育つ暖帯性常緑樹ですが、馬梁里ツバキの森にあるツバキはこの強い風の影響で高さが2メートル前後までしかなく、横に広がるように成長しています。
馬梁里ツバキの森にはツバキをめぐる言い伝えも残っています。
およそ500年前、馬梁の水軍の武官・水軍僉使(スグンチョムサ)が、海辺で成長する花々をたくさん増やせば、村に笑顔の花が咲き、村が栄えるだろうというお告げを夢の中で見て、翌日海辺に行ってみると本当に花があり、その花をさらに育てて増やしたといういい伝えが残っています。
この言い伝えが始まった後も村の人々は毎年陰暦の正月にここに集まり、大漁と海での無事を願う祭祀を行っているといいます。
現在、この森は村の防風林の役割も果たしています。またこの地域は地球の自転・公転の関係で西海(ソヘ)の海岸で日の出や日の入りを同じように眺めることができ人気を博している場所でもあります。
馬梁里には大規模な発電所があり、発電所の裏手にある道を歩き、丘の石段をしばらく上がっていくと、丘の上に冬柏亭(トンベクジョン)という東屋があります。
この丘に生えているツバキの木は距離を置きつつ植えられており、木の形は円形に近い形になっています。ここのツバキは防風の目的で植えられたということですが、風を遮る役割はあまり果たしていないようです。
*馬梁里ツバキの森のもうひとつ別の見所・冬柏亭*
馬梁里ツバキの森は西都(ソド)初等学校からおよそ4.5キロメートル離れた海辺の小高い丘の上にあります。
丘を少し上ると冬柏亭というこじんまりとした東屋があります。この近くにおよそ80本ほどのツバキの木があちらこちらに植えられています。
一方、馬梁里ツバキの森は韓国で数えるほどしかないツバキの森で、ツバキが育つ北限線の上に位置しており、植物分布の上においても価値が高い森となっています。
また豊漁祭や昔から伝承する言い伝えが残る森としても有名で、その文化的価値も高く、天然記念物に指定され保護されています。
椿の木はチャノキ同様、ツバキ科ツバキ属に属する木で、韓国をはじめ、日本・中国などの暖かい地方に分布しています。韓国では南部の海岸や島に自生しています。花は初春に開花し、その花はとても美しく、開花の時期によって春柏(チュンベク)、秋柏(チュべク)、冬柏(トンベク)と呼んでいます。
馬梁里のツバキの木は春柏常緑闊葉喬木で、葉が厚く、表面が濃い緑色で光沢があり、葉が多くびっしりと付いていて大変美しく見える木です。それだけではなく、晩冬から咲く真紅の花は晩春まで満開で、長い間その美しさを眺めることができます。
* 龍王に祭祀を執り行う建物、馬梁堂チプ*
およそ500年前、ここに住む村の人々はいかだに乗って海で魚を獲っていましたが、荒れる海で命を落とすことも少なくありませんでした。
そんなある日、夫と息子を失ったとある老婆がその海原から龍が昇天したのを見て、龍王を手厚く崇めれば禍を逃れることができる、とふと思いました。その白髪の老人は夢の中で海岸の砂浜で棺に入っている先皇5人を見つけ、それと同時にツバキの種を手に入れました。先皇は神霊を祭る祠・神堂に祀り、ツバキの種はその祠の周りに植えました。その種は森の85本の椿の木へと成長し鬱蒼と生い茂りました。
毎年正月の最初の日にはここ馬梁堂チプへと上り、3日目まで祭祀を執り行っており、この風習は今日まで継承され、祭祀を行ってからというものの海で漁を行っても禍が起きなかったと伝えられています。
祭祀は船艙祭、読経、テジャビ、マダン祭、龍王祭、村の人々が共同で道で行う祭儀・コリ祭と続きますが、それに先立つ祭祀が始まる数日前には各家庭から米を一枡ずつ供出してもらい、また神堂近くには豊漁、万船(大漁)を祈願する漁船旗数十本を立てたり、祭祀を執り行う人の衣装を準備して祭祀に備えます。
赤裳山史庫址(적상산사고지)
2024-04-08
チョンブク特別自治道ムジュ郡チョクサン面サンソンロ960
1592年の壬辰倭乱のときにソウルの春秋館をはじめとした全国の史庫が焼失し、春秋館を除いた鼎足山・太白山・妙香山・五台山などに新しい史庫を設置することになりました。1614年に天恵の要塞として知られた茂朱の赤裳(チョクサン)山に実録殿を建てて妙香山の実録を移し、1641年には璿源(ソンウォン)閣を建てて王室の族譜である『璿源録』を保管していました。後に日本により史庫が廃止されるまで、300年以上国家の貴重な国史を保存してきた韓国5大史庫の一つで、全羅北道記念物に指定されています。
この史庫跡は残念ながら赤裳揚水発電所ダムが建設されて水没し、安国寺とともにダムの上側に移転を余儀なくされました。赤裳山は四方が切り立った岸壁で、絶壁周辺にはカエデの木が多く、秋には山全体が赤いスカートを履いたように見えることから「赤裳山」という名前が付きました。
石圃展望台(석포전망대)
2020-07-15
慶尚北道 鬱陵郡 北面 天府里
+82-54-790-6392
「石圃展望台(ソクポジョンマンデ)」は、美しい神秘の島、鬱陵島の北面の端に位置し、小さな漁村・石圃村にあります。鬱陵島には、3つの望楼(高台に建てられた監視用の楼閣)がありますが、この中で東側にあるのがこの石圃展望台です。1905年に設置された展望台は、日露戦争以前から望楼の役割をしており、日本がロシア軍艦を観測するために1945年まで使用されていたことが知られています。
石圃展望台は、鬱陵島と韓半島の間にある東海を展望できる位置にあり、展望台には2階建ての八角展望台とデッキ、望遠鏡などがあります。八角展望台に上がると鬱陵島3大秘境である孔岩(おばけ岩)、観音島、三仙厳とともに竹島(チュクト)、北側海岸絶景など天恵の自然景観を一望できます。展望台の下には、石圃休憩所がある他、石圃展望台から内水田日出展望台までつながる石圃昔の道トレッキングコースがあります。
論山イチゴおじさん農場(논산 딸기삼촌농장)
2021-05-29
忠清南道 論山市 魯城面 丙舎里423-9
以前はデパートやスーパーと取引していたイチゴおじさん農場ですが、消費者に安くイチゴを提供したいという思いから、現在はイチゴ体験農場を運営しています。ここで栽培されているイチゴは長年にわたる自然農法・エコ農法によって「低農薬認証」を受けています。安全で高品質なイチゴを消費者に届けるため、イチゴおじさん農場は日々努力を続けています。
慶州 東宮園(경주 동궁원)
2017-12-18
慶尚北道 慶州市 普門路74-14
韓国初の動植物園とされる新羅王宮の別宮「慶州東宮と月池」を現代風に再現した東宮園(トングンウォン)は、東宮植物園、農業体験施設、バードパークから成っています。そのなかでも特に目を引くのが植物園で、新羅時代の伝統的な建築デザインの要素を取り入れた、ガラス張りの一風変わった建物となっています。
閑麗海上国立公園(南海)(한려해상국립공원(남해))
2020-12-24
慶尚南道 南海郡 尚州面
+82-55-860-5800
閑麗海上国立公園は1968年韓国初の海上国立公園に指定されました。公園の範囲は南側巨済只心島~麗水梧桐島に至り、6地区(巨済、統営、泗川、河東、南海、麗水梧桐島)に分けられます。総面積535.676平方キロメートルのうち海上面積が76パーセントを占め、海洋と島嶼、陸地がもたらす地形景観に優れており、毎年100万人以上の人々が訪れます。
エキスポ海洋公園(엑스포해양공원)
2022-12-28
全羅南道 麗水市 博覧会キル1
「エキスポ海洋公園」は海に面した水辺公園を散歩したり、ダイナミックなマリンスポーツプログラムやここでしか見られないマルチメディアBIG-Oショーを楽しめるだけでなく、我が家のようにくつろげるゲストハウスも完備しています。また、国際的な会議施設も整っており、各種の会議・展示・セミナーといったイベントを行うのにも最適の場所です。
舒川 タルゴゲカラムシ村(서천 달고개모시마을)
2021-02-03
忠清南道 舒川郡 華陽面 華韓路504番キル5
+82-41-950-6380
夕暮れ時、空が段々暗くなり月が徐々に明るくなってくると、なぜ、ここが「タルゴゲ(月の峠)カラムシ村」といわれるのかがわかってきます。何も遮るもののない平らな大地に立ち、全身に月の光を浴び、月明りに酔いしれていると、遠くからマガモの群れの飛び立つ音が聞こえてきます。
カラムシは千年という非常に長い歴史を誇り、その由来も実に神秘的です。百済時代、ある老人が夢枕に立ったことで乾芝山のふもとにカラムシが発見され、その歴史は始まりました。三国時代から発達してきた天然繊維であるカラムシは「トンボの羽」と表現されるほど細く、纎細な織物です。高麗時代には中国・明への貢物、朝鮮時代には献上品とされたほどの逸品です。
韓山カラムシの伝統をいまに受け継ぐこの村には、多くの「カラムシ織技能保有者」がいます。3ヶ所設けられた体験場では、カラムシを採り、紡ぎ、織るといった製作過程を体験することができます。名人の作ったカラムシ織りの服を着てみることもでき、大量生産品との違いを感じることができるでしょう。その他、天然染料を使った染色体験、カラムシを使ったお餅やカルシウム満点のカラムシ茶、カラムシチヂミ、カラムシパン、韓菓などを作るプログラムもあり、子どもから大人まで楽しめます。特に韓菓は、村特産の穀物が使われるため、それだけ手間隙がかかっています。さっと揚げた雑穀をハチミツとからめ、適度な固さになるまで麺棒で平らにのばしカットします。作る楽しさと食べる楽しさ、両方味わうことができるプログラムとなっています。
ARTEE人力車(아띠인력거)
2022-09-15
ソウル特別市チョンノ区プクチョンロ5ギル43
ARTEE人力車(ARTEE RIDERS CLUB)は人力車で巡る観光ツアーを提供する会社です。北村、西村、明洞、貞洞地域を中心に、裏路地や小路をガイドしています。







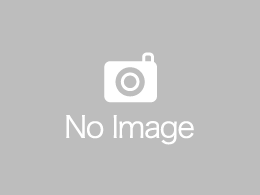
 日本語
日本語
 한국어
한국어 English
English 中文(简体)
中文(简体) Deutsch
Deutsch Français
Français Español
Español Русский
Русский